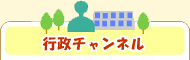Z-CAN 日本の伝統「二十四節気」と「太陰太陽暦」の豆知識!
すっかり冷え込むようになって、上着が必需品ですね。
季節の変わり目ということで、今回は日本で古くから伝わる、「二十四節気」と「太陰太陽暦」の豆知識を紹介します!
二十四節気とは?
| 二十四節気は太陰太陽暦を使用していた時代に、季節とのずれを調整するために使われてきました。 1年を4つの季節に分け、それぞれを更に6つに分けて24等分し、季節感を正確につかんで農作業に支障をきたさないように考え出されたそうですよ。 夏至・冬至、春分・秋分は馴染み深いですよね。 更にその中でも、立春・立夏・立秋・立冬は季節の変わり目の基準になっていて、年賀状等でも使われています。 |
 |
太陰太陽暦とは?
| 日本では明治6年までは太陰太陽暦を使用していたのをご存知ですか? 太陰太陽暦は古代中国から伝わったもので、月の満ち欠けを基準とする太陰暦と太陽の高度を基準とする太陽暦が合わさったものなんです。 太陰暦と太陽暦では1年の日数が11日異なるため、季節とのずれを修正するため4年に1度の周期で閏月が設けられていました。 現在では古代エジプトを起源とするグレゴリオ暦(太陽暦)が使われていて、太陰太陽暦を旧暦、グレゴリオ暦を新暦と呼んでいます。 |
 |
さいごに
| 新暦が浸透している今でも旧暦の文化は形を変えて親しまれています。 例えば、七夕は旧暦では月の満ち欠けで時期が決まって、日付はその年によってまちまちだったそうですが、新暦では毎年同じ日付の7月7日に行われていますよね。 二十四節気も新暦になることでずれが生じなくなったため、季節感を正確に掴むというよりは、季節を感じるものになっているように思います。 最近では、11月7日に立冬を迎えます。冬にかけて寒さ対策をしていきましょう^^ |
 |
情報提供 |
快適な住まいと、生活の知恵を大切に! 生活応援隊の皆様、ありがとうございました! |