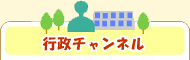Z-CAN 勤労感謝の日
| 国民の祝日の一つである「勤労感謝の日」の本来の意味をご存知ですか? 最近ではあまり知られていない、「勤労感謝の日」の歴史をご紹介します! |
勤労感謝の日って?
| 勤労感謝の日は「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」(祝日法 第2条)を趣旨として、1948年に定められました。 勤労感謝の日自体に由来があるわけではなく、元々は「新嘗祭(にいなめさい)」というお祭りだったというのを、知らない方も多いのではないでしょうか? 農業国家である日本は、古くから神に五穀の収穫を祝う風習があり、収穫物に感謝する大事な行事として、飛鳥時代の皇極天皇の時代に始まったと伝えられています。 戦後にGHQ(=連合国軍最高司令官総司令部)の占領政策により天皇行事・国事行為から切り離され、勤労感謝の日と改められました。 |
 |
なぜ11月23日なのか?
| 11月23日という日付に深い意味はなく、たまたま改暦が行われた1873年の11月の下卯の日(2回目の卯の日)が23日だったことから、11月23日に固定されただけだそうです。 ちなみに、勤労感謝の日は固定日の休日では最も長く続いていて、日本国民に最も定着している休日でもあります。 |
新嘗祭について
| 新嘗祭は収穫祭にあたるもので、天皇がその年にとれた新穀を天神地祇に供え、農作物の収穫に、天皇と国民が一体となって感謝して喜び合う全国民的な祭典だったそうです。 1908年に制定された皇室祭祀令では大祭に指定され、同法が廃止されてからも宮中では従来どおりの新嘗祭が行われました。現在でも11月23日には伊勢神宮を含め全国の神社で新嘗祭が行われています。 「勤労感謝の日」「新嘗祭」の本来の意味を知り、食物の大切さとありがたみを認識しましょう! |
 |
情報提供 |
快適な住まいと、生活の知恵を大切に! 生活応援隊の皆様、ありがとうございました! |